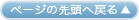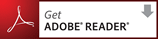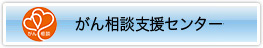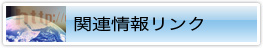第1回幹事会が令和7年6月19日(木)にWebにより開催され、兵庫県内の地域がん診療連携拠点病院等47病院及び関係病院等2施設・2団体の代表者が参加した。
※ 幹事、事務担当者等、代理を含め105名が出席 (欠席施設等:1施設、1団体)
(1)前回幹事会及び協議会議事録の確認
今年2月13日開催の第2回幹事会議事録及び4月17日開催の第20回協議会議事録は、本協議会のホームページに掲載されているので、内容の確認をしていただきたい。
(2)がん対策について (資料2/PDF: 942KB)
①兵庫県内のがん診療連携拠点病院等の指定状況等
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針に基づいて、がん患者の居住する地域にかかわらず等しく状態に応じた適切ながん医療や支援等を受けることができるように整備を進めてきた。
国指定拠点病院は、「がん圏域1圏域に対して1か所は整備する」となっているところ、兵庫県においては、がん圏域10に対して18施設がある。県立丹波医療センターと赤穂市民病院は、地域拠点病院がないがん圏域で拠点病院との連携を前提に地域がん診療病院として指定している。近畿中央病院は指定要件の充足状況が不十分であると判断された場合の経過措置中となっている。
県指定拠点病院は6施設となり、去年の4月より2施設減っている。西宮市立中央病院は経過措置で2年が経過し、県立西宮病院との統合前提もあり、日本医療機能評価機構の審査を受けていない、放射線治療医が配置できていないなどの点から県指定から外れた。西脇市立西脇病院は、院内のがん患者登録数、放射線治療の件数が満たせず、2年間の経過措置で今年の4月に県指定から外れている。
また、新たにツカザキ病院が準じる病院に加わっている。
がんの先進的医療に特化した治療を提供している医療機関として3か所あり、がんゲノム医療拠点病院(国指定)が2か所、がんゲノム医療連携病院8か所に加えて、今年の6月1日より市立伊丹病院が大阪大学医学部付属病院選定となっている。小児がん拠点病院(国指定)は、県立こども病院で変更はない。近畿ブロックの小児がん連携病院も変更はない。
②令和7年度当初予算
全体的に大きな変更はないが、昨今の厳しい財政状況の中で必要な財源の確保に努めている。がんに関する各施策をがん対策の柱に沿って分類して記載しているが、「がん予防推進」の「生活習慣改善の推進」の中で「データおよびICTツール活用した市町健康づくり支援事業」は、前年度の10,175,000円から19,500,000円に増額しているが、これは健診データを用いた健康状態の把握などの事業で市町に対する人材派遣費として追加となっている。
「早期発見の推進」の「検診機会の確保と受診環境の整備」の中にある「集団検診車整備事業」は数年に1回の整備なので、今年度は該当が0となった。
「医療体制の充実」の「個別がん対策の推進」の中にある「粒子線治療資金貸付制度の実施」、「がん患者の療養生活の質の維持向上」の「在宅看護体制機能強化事業」は実績に合わせた減額となる。また、その下の「新 24時間対応在宅介護サービス参入促進事業」は、既存事業の看護小規模在宅サービスを新規事業として整備したもので事業委託料となる。
③がん診療連携拠点病院の指定要件に関するアンケート調査結果
がん対策基本計画において、国および都道府県は、がん医療が高度化する中で引き続き質の高いがん医療を提供するために、地域の実情に応じて均てん化を推進するとともに、持続可能ながん医療の提供に向けて拠点病院等の役割分担も踏まえた集約化を推進するとされている。こうしたことを踏まえて、がん診療連携拠点病院の現状課題を把握するために、国指定拠点病院及び県指定拠点病院にアンケートを実施した。
調査内容は診療実績、診療従事者確保の困難の有無について、次回の更新予定である令和9年3月頃を予想して回答してもらった。
国指定がん診療連携拠点病院は18施設である。診療実績としては、9割の病院が要件を満たすことが困難な項目はないという回答であったが、放射線治療延べ患者数に関しては3病院が満たさない予想であり、機器更新等で使用できない、あるいはそもそも患者数を満たすことが難しいという意見や、手術件数、薬物療法、放射線全てにおいて患者数要件を満たすことが困難だというような意見があった。医師の確保に関しては、9割の病院で要件を満たす。一部で放射線診断医、放射線治療医、それから精神科医、病理医、緩和ケア医、と外科医以外の職種で確保が困難な病院もあり、専従要件を専任要件に緩和、常勤を非常勤に容認などの緩和措置を希望するという意見が出ている。医師以外の医療従事者の確保は、医師確保に比べるとほぼ問題がなさそうであるが、僻地において人材確保が困難であることが伺われる。全体を通して、回数よりも質の評価をしてほしい、非都市部での人材確保が課題であるという意見があった。
県指定の7病院でも、放射線治療患者数においては、3施設で薬物治療、手術に関して基準維持が困難という回答があった。原因として、コロナ以降の患者数減少に加えて医師確保も課題となっている。国指定拠点病院同様、放射線治療医、薬物治療医、それから精神科医の確保が困難となっている。県指定拠点病においては、「集約化をしたほうがいいと思う領域」について質問をしたが、1施設以外は「なし」という返答であった。現在の指定要件に関しての妥当性については、5施設が妥当、2施設は妥当ではないと回答されており、県指定拠点病院では診療報酬の加算対象にもなっていないこと、そのため、研修要件があるものについても国指定拠点病院が優先のため受講できないことがあることも考慮してほしいという意見があった。また、治療まで至らない「がんを診断する能力」についても評価されるべきではという意見もあった。
これらを踏まえて、国指定拠点病院については、令和10年度予定の指針見直しを注視していくこと。県指定拠点病院については、患者確保、人材確保で困難感がある病院に対してどのような対応が考えられるか、健康づくり審議会対がん戦略部会、がん診療連携推進専門委員会で検討することも考えていくこととしている。
〇質疑応答
- ⇒ 公立病院の赤字というのはとても大きな問題で、県立、市立の病院がこれから潰れるようなことがあれば、兵庫県の医療が崩壊していくことになる。県立病院については、決算報告を分析してみたが、入院とか外来の機能がとても少なくて赤字になっているというわけでなく、外来も一生懸命やっているということで、やっぱりこれは県としても何らかの税金を県立病院に投入して維持をするということは考えられないだろうか。
- ⇒ 県立病院の経営状況に関しては、その地域の医療を確保していくという意味では、やっぱり役割分担と、連携でカバーをしていくという方向性になっている。がん圏域内での連携とか、地域医療連携推進法人など、地域で進めてもらうようにしている。税金を病院運営に投入することに関しては、ここでは申し上げられない。
- ⇒ 赤字が大きくなる前に県立病院が健全な経営が続けられるような体制をとっていただきたい。
- ⇒ あらゆる病院がいろんな策を講じて努力して増収にはなっているが、物価高騰を抑制することと、診療報酬を底上げしないとどうにもならないのではと思っていて、県にも申し上げているし、引いては国に考えてもらわないといけないことではある。
〇意見・提案
- ⇒ 国指定拠点病院の指定要件を自由に変えることはできないが、県指定拠点病院に関しては、指定要件の緩和も再検討していきたいと考えている。(議長)
- ⇒ 2013年に設立された神戸低侵襲がん医療センターの設立目的は、1つ目は神戸大学病院の治療機能を補完すること、2つ目は神戸市内のがん診療準拠点病院の治療機能を担うこと、3つ目は兵庫県全体の高精度放射線治療を担うことであった。この集約化によって治療のレベルが上がると同時に、実質的な経費もかなり節約ができている。当院には、放射線治療装置が3台あって、この10年間で約40億円の経費がかかっている。年間延べ1200件前後を分散すると、通常は、5台、もしくは6台の治療装置が必要になり、経費的にも約2倍になってしまう。そのため、このような集約化、共同利用というのは、今後ますます必要になると考えており、この4月1日に地域医療連携推進法人というものを立ち上げた。ここに全部で10施設が加わっていただいており、こういう仕組みを今後県の指定要件の中に組み込んで検討していただければと思う。(神戸低侵襲がん医療センター 院長)
- ⇒ 放射線治療の症例数が足りないとか、治療費が足りないという問題はあると思うので、仰る通り、放射線治療の部門は神戸低侵襲がん医療センターと連携して1つの拠点病院として認めるとか、そういう発想も必要であると考える。(幹事長)
- ⇒ 現在厚生労働省の中で、がん診療提供体制のあり方に関する検討会という検討会がある。発端は主に外科の先生方が今後どんどん減ってくるので、外科治療を集約化しないとがん治療ができなくなるだろうということ。2040年のがん患者さんの推移を見込んで、どのように集約化と均てん化をすべきかという議論が進んでいる。外科、主に日本癌治療学会と日本臨床腫瘍学会、日本放射線腫瘍学会も入っており、放射線治療に関しては、がん診療連携拠点病院を中心に、医療圏またはそれに準ずる拠点に集約する方向で議論が行われていると理解している。その報告書を待って、方向性が明確になってから、再度詳細に検討するのがいいのかなと思った。(神戸大学医学部付属病院 幹事)
(3)幹事会運営要領の改正について(資料3/PDF: 334KB)
国指定拠点病院等は、第19回協議会の開催以降指定状況に変更はなく協議会測に改正はない。今回の幹事会運営要領の改正は、令和7年3月26日をもって新たにツカザキ病院が準じる病院に指定され、令和7年4月1日をもって西宮市立中央病院、および西脇市立西脇病院が県指定拠点病院から準じる病院に指定されたことに伴う改正である。なお、運営要領の改正施行日は、第20回兵庫県がん診療連携協議会開催日の令和7年4月17日となる。
(4)協議会・幹事会並びに各部会の令和6年度活動報告及び令和7年度活動計画について
(資料4/PDF: 13.9MB)
①「協議会・幹事会」関連
令和6年度は、4月11日に第19回がん診療連携協議会をWeb開催、6月6日に第1回幹事会をWeb開催、令和7年2月13日に第2回幹事会をWeb開催した。10月19日に第14回ひょうご県民がんフォーラムを開催、テーマ「がんと診断されたあなたに~患者力を高めるには~」で、会場参加71名、Web参加60名の計131名の参加があった。令和7年度は、4月17日に第20回がん診療連携協議会をWeb開催、本日6月19日に第1回のがん診療連携協議会幹事会をWeb開催、第2回幹事会は、令和8年2月5日Web開催の予定である。今年度のひょうご県民がんフォーラムは11月8日(土)開催、テーマは「みんなで話そう、これからのこと~アドバンスケアプランニング(人生会議)のすすめ~」である。
②「研修・教育」部会関連
昨年は、11月22日、29日、12月6日にがん看護コアナース育成セミナーを開催した。セミナーの開催は、すべてハイブリッドで開催。研修・教育部会セミナーは10月5日に開催、テーマは「消化器がんに対するロボット手術の現状と未来」、会場23名、Web 37名に参加いただいた。放射線セミナーは10月12日に開催、テーマは「直腸がんの診断と治療-update-」、会場32名、Web 125名、計157名の参加をいただいた。検査セミナーは12月14日に開催、テーマは「見えない敵とどう戦うか~がんと微生物に対する両面作戦~」、会場41名、Web 53名、計94名の参加をいただいた。薬剤セミナーは今年の2月8日に開催、テーマは「ICIによるirAE・薬剤師外来」会場22名、Web 236名、計258名の参加をいただいた。がん診療連携拠点病院を対象とする、「第9回 兵庫県がん化学療法チーム医療研修会」は、11月30日に開催、テーマ「がん治療における妊孕性温存」ということで、3チーム13名参加した。「第14回 ひょうご県民がんフォーラム」は、前述の通りである。
今年度の計画は、がん看護コアナース育成セミナーは、テーマを「多様化するがん患者の一人ひとりの力を信じ、その力を引き出し、高める意思決定支援」とし、体験研修は11月4日から14日のうちの1日、講義・事例検討を11月21日、28日、12月5日に計画をしている。募集人数は30名である。がん診療連携拠点病院を対象とする「第10回 兵庫県がん化学療法チーム医療研修会」は、今年の秋開催だがテーマや開催方式は未定である。
セミナーは、今年度もすべてハイブリッド開催、会場は神戸市教育会館。研修・教育部会セミナーは10月11日で、テーマは「膵がんの診断と治療の最前線」である。放射線セミナーは10月25日で、テーマは「乳がんの診断と治療-update-」である。検査セミナーは12月6日で、「がん薬物療法と超音波検査(仮)」である。薬剤師セミナーは来年の1月31日で、テーマは「がん治療関連心機能障害(仮)」である。「第15回 ひょうご県民がんフォーラム」は前述の通りである。
PDCAサイクル実施計画は、昨年度に関してはほぼ計画を達成したと考えている。1つ提案させていただいたのは、セミナーは土曜日だけでなく平日開催も検討していただきたいと思っている。
③「情報・連携」部会関連
令和6年度は、部会を年4回から年2回に減らして、各施設のご負担を減らすという改革の初年度となっている。初回の部会は9月に実施、就労支援グループの3年間のプロジェクトの総仕上げということで開催した。3月には、全体の部会とピアサポーターフォローアップ研修&相談員との交流会を開催した。事務局会議も予定通り開催した。
令和7年度に関しても基本的には似たような形を予定しており、部会は9月と3月の2回開催、事務局会議は奇数月に実施という形になっている。相談員研修関連、ピアサポーター関連についても推進していく。
PDCAサイクル実施計画は、令和6年度は概ね予定通り達成した。令和7年度の実施計画は、小グループを3つに再編して、相談員研修グループ、ピア育成推進グループ、質評価グループとした。兵庫県の中で指導者を継続的に育成していかないと、一部の病院に偏りが出始めており、退職や移動で一気に体制が崩れることが懸念されている。相談員研修グループでは、今年度から皆様のご協力を得て相談員研修指導者の研修も分担して行っていくという形になっている。ピア育成推進グループに関しては、引き続き、兵庫県の疾病対策課と協力してピアサポーター要請とフォローアップ研修会、交流会などを行い、ピアサポート活動の質向上に向けた支援に取り組む。
国の会議でも情報連携部会は節目を迎えており、働き方改革、その他持続可能性というのも議題になっており、国全体の情報連携部会も改革を行っていくとなっている。昨年度からも引き続きお願いしているが、兵庫県としても、県の課題としてそれを国に上げていく、現場の意見を吸い上げるという、2つの働きが必要になってくるので、それぞれ効率よく行うために、部会の会議には組織的、管理的なことを把握していただいている方にもぜひご参加いただくよう人事や体制などのご協力を引き続きお願いしたい。
④「がん登録」部会関連
部会は6月に開催をした。院内がん登録実務者ミーティングは年2回開催、1月開催時に2022年の「施設別・部位別院内がん登録数・治療数」の集計結果を提示し、公表案として3月の幹事会に提出、承認されたので、現在がん診療連携協議会のホームページに公表している。
都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会のがん登録部会が5月28日にWeb開催され参加している。院内がん登録関連本年の予定とQIデータ提出等に関する予定の報告があった。全国がん登録実務者研修会は、9月20日から10月31日にかけて動画配信で実施している。
がん登録部会の令和7年度の活動予定は、7月11日にがん登録部会の開催を予定している。院内がん登録実務者ミーティングの開催も2回予定していて、昨日、都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会のがん登録部会に参加した。PDCAサイクル実施計画は、「がん診療情報を収集、分析する体制整備」「がん登録実務の精度向上」「全国がん登録情報の予後情報還元申請」の3つを課題に上げている。収集分析はより患者等に役立つデータのホームページ掲載、がん登録実務の精度向上は、講義を含めた実務者ミーティングの開催や研修参加、予後情報還元申請に関しては、セキュリティ対策整備が課題であるが、これに対して相談支援を行い、情報共有を図っていきたい。令和7年度もこの3つについて引き続き取り組みを進めていく。
⑤「緩和ケア」部会関連
令和6年度の活動について、部会は4回Webで開催した。それに伴い、部会の運営事務局会議を毎月第1金曜日Webで開催している。
小集団活動の報告。令和6年度緩和ケア研修会指導者の会は、今年2月9日にWeb開催、20名が参加。令和6年度緩和ケアフォローアップ研修会は昨年12月7日に開催、14名が参加している。第15回兵庫県緩和ケアチーム研修会は、今年2月9日にWebで開催、77名が参加。これは、緩和ケアチームのメンバーにご参加いただいている研修会である。緩和ケアチームピアレビューは、各施設の緩和ケアチームをピアレビューするという活動になるが、昨年、2施設が参加した。第1回が令和6年10月13日、対象施設は神戸市立西神戸医療センター。第2回が12月4日、対象施設は県立はりま姫路総合医療センターで実施している。続いて、症状緩和のための専門的治療体制に関する実態調査ということで、例年実施している調査になるが、拠点病院における神経ブロック療法、緩和的放射線治療、緩和IVRの実施体制に関する実態調査を行った。こちらの内容は、がん診療連携協議会のホームページで情報公開しているので、ご参照いただければと思う。最後に、都道府県がん診療連携拠点病院の連絡協議会の緩和ケア部会。これは部会長が参加をしている。
今年度の緩和ケア部会に関しては、昨年の年4回から年3回に削減している。第1回は、先日5月22日に開催、次回は9月、3回目は令和8年1月に実施予定となっている。運営事務局会議に関しても、毎月開催から偶数月の開催に変更した。
小集団活動の運営に関しては、基本的には令和6年度から継続していくが、緩和ケア研修会に関する検討会は、各施設緩和ケア研修会はそれほど支障なく開催できているので、今年度をもって終了、小集団の活動方法は検討していく。兵庫県の緩和ケアに関する課題を踏まえて新たな小集団活動を作っていきたい。今年度のフォローアップ研修会は、市立伊丹病院と近畿中央病院に担当していただく。開催日は未定である。第16回緩和ケアチーム研修会は、北播磨総合医療センターが当番幹事として開催を予定している。これまで休日開催をしていたが、今後は平日のできるだけ勤務時間内、もしくは、勤務時間終了後直後で少し時間を短縮して開催できればということで検討している。緩和ケアチームピアレビューは、今年度1施設を予定している。症状緩和のための専門的治療体制に関する実態調査に関しては、例年通り実施をしたいと思うので、各施設にアンケート調査にご協力いただきたい。
そこを踏まえてPDCAサイクル実施計画になるが、5つの小集団活動それぞれに作成している。基本的には令和6年度は計画通り達成をされている。令和7年度もどれも継続ということにしているが、緩和ケア研修会の課題に関しては、一応今年度終了という形で計画を進めていく予定である。
⑥「地域連携」部会関連
昨年度の活動報告について、一昨年度のがんパスの使用状況を調査した。令和5年度は新たに1,485件のがんパスが使用されて累計14,339件となった。その中でいくつか課題が見つかったので、各ワーキンググループで検討しガイドラインあるいは取扱規約に応じて修正した。使いやすいものになったので積極的に使用していただきたい。
がん診療における地域連携の現況に関しては、Webによる退院前カンファレンスと遠隔診療、がんゲノム診療についてのアンケートを行った。令和5年度のWebによる退院前カンファレンスは485件、遠隔診療は167件であった。がんゲノム診療に関しては、がん遺伝子パネル検査を実施した、もしくは実施している施設に患者を紹介した施設が20施設。最終的に治療につながったものも平均で16%ということで、一般的には10%程度といわれているので、比較的兵庫県ではうまく繋がっているように思う。
今年度の活動としては、同様にがんパスの使用状況を検討する。運用上の課題を抽出し、改変が必要なものに関しては改変を加えて活用を図りたい。地域連携に関する課題について、PDCAサイクル実施計画は概ね達成、今年度も引き続き取り組む。
がんの地域連携パスについて、2025年3月末時点でアンケート調査を行った。令和6年度の登録件数は1,729件となり、一昨年度に比べて244件増えている。国指定拠点病院の18施設においては、少なくとも1つ以上のパスが使用されている。県指定拠点病院並びに準じる病院に関しては調整中の施設もあるが、可能な範囲で活用していただきたい。使用状況は病院によって特徴があるので、特徴を見ながらいろんな課題について、取り組んでいく必要がある。パスの逸脱に関しては全体的には10%未満ということで、比較的目標には達しているが、肝臓がんが30%、肺がんが23%と比較的高い。理由は、がんの再発、患者さんの社会的要件ということで、やむを得ない部分はある。パスのバリアンスに関しては、全体で0.2%である。肝がんに関してはなかなか難しいところがあって、2.5%とバリアンスの発生が多いということが示された。
パスの運用について、専門領域の先生と連携しているかのアンケートを行った。その中で、大腸がん、胃がん、肺がんにおいては、専門外の先生とも多数つなげている実態があった。がん患者の高齢化という背景もあり、がんの種類にもよるが一般診療の先生との連携も必要と思われる。一般的なフォローは開業医の先生に行っていただき、緊急時の対応は拠点病院といった形など、患者さんを見ながら連携していければと思う。
Webによる退院前カンファレンスについては、半分ぐらいの施設が利用しているが、結果的に件数は減ってきている。また、遠隔診療(リモート診療)は、全体の約4%しか行えていない。原因としては、セキュリティの問題、診察室に回線がないといったことがあるが、コロナ禍が明けてやめてしまったということもある。本当はいい診療方法だと思うが、face to faceでやった方がいいとの意見もあり、なかなか定着しにくい。
がんゲノム診療については、43施設から回答があり、治療につながった方が14%と兵庫県では強く連携してうまく治療に繋げられている。ただ、3月末でアンケートを取ると、治療につながるかどうかわからない症例があるということで、集計は1月、もしくは12月で切った方がいいのではという提案もあり、皆さんに相談させていただきたい。
先ほどの神戸低侵襲がん医療センターの提案のように、がん治療機器の共同利用をシームレスに行うといった形で、がんの治療体制を新たに構築している地域もあり、こういった試みが他にもあれば教えていただきたい。また今後は、がんパスの非専門医との連携に関してどのように安全につなげられるか、手順書の作成などもワーキンググループの先生方と考えていきたい。
(5)小児がんの進捗状況について (資料5/PDF: 3.3MB)
現在、小児がんは、第4期のがん対策推進基本計画に則って、第3期目の小児がん拠点病院事業が展開されており、今年度で第3年目ということになり、来年また審査を受けて更新が可能かどうかということになってくる。
小児がんは全体でもわずか2,000人から2,500人、3,000人ぐらいしかなくて著しい希少がんである。その中で、造血腫瘍が4割から5割ぐらい、脳脊髄腫症が3割弱、その他、様々ながん種がここに含まれる。拠点病院事業が始まる前は、全国で200近くの病院にこういった症例が分散して治療をしていて、経験も実績もなかなか積み上げが進まなかった。治療の提供体制の集約化と均てん化というのが大きな命題になって進んでいる。
小児がん拠点病院としては、全国に15の病院があり、近畿には4つの病院がある。京都府立医科大学付属病院、京都大学医学部附属病院、大阪市立総医療センター、兵庫県立こども病院の4つがある。
均てん化と集約化の実績については、全国の小児がんを扱う施設の中でも兵庫県立こども病院は、比較的たくさん症例を扱っている。それを支えるために人材をたくさん集めていただいており、小児血液がんの専門医が5名、日本血液学会専門医が8名、移植学会の認定が8名というチームで治療に当たっている。他の施設との連携が非常に重要となる。全体の拠点病院事業のデザインとしては、小児がんの拠点病院と準拠点病院のカテゴリ一1-Aの病院と合わせて、日本全体の小児がんのおよそ7割をカバーしようという計画で進んでいる。県内では、県立尼崎総合医療センター、それから神戸大学附属病院が準拠点病院ということで、共に小児がんの診療を担っており、兵庫県ではほぼこの3つの病院に集約されている。
他府県に視野を広げると、準拠点病院も拠点病院もないという地域がかなりあるので、これをどうするかということで今現在話し合いが進んでいて、人口が少ない地域でも、設備が整っていれば準拠点病院に指定していくという動きになっている。小児がんに対して様々ながん種に対応できない病院もたくさんあり、中国四国地域とかかなり広い範囲に視野を向けて、救急集中治療を含めて、あらゆる小児がんに対応可能な状態を作って進めている。人材育成についても、香川大学医学部付属病院の小児チームと連携をして研修制度をスーパーバイズするという形で人材育成も一緒に担っている。
3年前に認可を得た遺伝子改変T細胞治療やCART細胞療法については、現在5例目の準備をしている。造血幹細胞移植についても、施設としては4床の無菌床を持っており、他府県からも症例を集めて診療を行っている。最近は、少子化のため良いドナーさんがなかなか見つからないこともあり、急性ないしは慢性のGVHD(移植片対宿主病)に対する治療についても強化を図っている。
兵庫県立こども病院の1つ大きな特徴として、隣に神戸陽子線センターがあり、全国あちこちから陽線治療の患者さんが紹介されてくるということで、小児がんに対する陽子線治療は全国で1番実績がある診療の施設ということになっている。昨年度は80名弱ぐらいの症例を全国から送っていただいて診療に当たっており、今年度も順調に実績を積んでいる。
ゲノム医療に関しては、NCCオンコパネル、FoundationOne®Liquid CDxは小児がんに対して適用が一部である。例えば、リキッドが小児に対して使えないとか、いろんな制約はあったが、小児がんに特化したGenMineTOP®がんゲノムプロファイリングシステム、あるいは造血器腫瘍遺伝子パネル検査「ヘムサイト®」が使えるようになったということで選択肢が増えていっている。広く使用されるようになったNCCオンコパネル検査を検査ラグ(入口戦略)の解消に位置づけてやっていきたい。出口戦略としては、ドラッグラグの解消を合わせて進めていきたい。人材育成が非常に重要となるので、兵庫県立こども病院でもこの4月から国立がん研究センター中央病院の小児腫瘍科の先生を東京から招きスタッフに加えた。こちらと連携を強化して、小児がん、希少がんの治験に積極的に参加をしていきたい。具体的には、今年度中にユーイング肉腫に対する国際共同治験の実施施設にノミネートされる予定である。年齢が15歳を超えた患者さんも一部受け入れができる体制で組んでいるので、何かあればお声がけいただきたい。
新しい制度として、ドラッグラグの解消のために仮承認という形で条件付き承認が昨年の10月から開始になっている。症例の少ない患者さんに適応の拡大とか、治験を進めるというのが、なかなか容易ではないということで、条件付き承認を行って、海外で十分な実績あるものについては、国内での治験を一部省略して本承認に持っていきたいという試みがされている。
移行期医療に関しては、神戸大学医学部付属病院や県立尼崎総合医療センターの先生方と連携して取り組んでいる。サバイブした患者さんが移行期を過ぎてから、どのような後遺症を持っておられるかということに注目して調査したところ、およそ6割の人に晩期障害があったという衝撃的なデータとなった。サバイブされた患者さんを、成人の先生方にどうやって受け継いでいくかということが非常に重要だと考えている。特に兵庫県内では、慢性疾患の移行期医療については、神戸大学医学部付属病院の中に移行期医療支援センターが設立されているので、そちらの先生方と協力をしながら患者さんが相談できる窓口をライフステージに応じて担保できるように連携を深めてやっていきたい。
また、療育療養環境については、兵庫県の教育委員会高等教育課の先生方と協力しながら、入院中の患者さんに中学校までではなくて高等教育についてもICTを使って授業を届けたい。どちらの病院であっても、教育委員会と共にお手伝いできると思うので、ぜひお声掛けいただきたい。
緩和ケアについては昨年度の診療報酬改定で手厚い増額が認めてられているので、医療の充実を図っているところである。緩和ケアの算定件数も増えており、特に小児緩和ケア診療加算というのが1日700点という診療加算がとれるようになった。
兵庫県立こども病院では、療養関係の改善を目指す過程で、ホスピタルファシリティドッグの導入を検討し、費用捻出のためクラウドファンディングを行っている。ぜひご支援を賜れたらと思う。
(6)その他 (別冊/PDF: 3.6MB)
・心血管フォローアップ手帳について(資料6-1/PDF: 164KB)
心血管フォローアップ手帳の作成において、皆様のご協力により大変幅広く対応できる内容になったと思う。手帳の利用方法は、兵庫県がん診療連携協議会のホームページからダウンロードをして印刷できるようになっているので、ぜひご使用いただきたいと思う。
〇質疑応答
- ⇒ 非常にいい取り組みだと思う。これは兵庫県内だけでとどめておくのか。
- ⇒ もちろん日本全国が使っていただけるようにすることが今後の課題である。
- ⇒ 腫瘍循環器学会で取り上げてもらっては
- ⇒ 学会組織として何か取り組んでいただけることがあるのなら、本当に願ってもないことである。広げていただけるような手段があるのであれば、ぜひともおliいしたい。
- ⇒ AYA世代のがんの患者さんが増えているということもあるし、長期にわたる放射線治療や抗がん剤で心筋障害を起こすということが今トピックスになりつつある。気になる患者さんがおられたら、がんセンターにかかっている、いないにかかわらず心血管フォローアップ外来をご紹介いただければと思う。
・兵庫県の希少がん対策について(資料6-2/PDF: 332KB)
前回(令和7年2月)の幹事会でご承認いただいた兵庫県希少がん対策ワーキングを6月10日に行った。国指定拠点病院と地域のがん診療病院にご参加いただき、全14施設16名に参加いただいた。
まずこのワーキンググループ設立の目標は、希少がん患者が必要な情報にアクセスでき、そこから速やかに適切な医療につながれることを目指すこと。取り組み事項は、拠点病院を中心に役割分担を整理して施設間での連携を促進すること。希少がんに関する情報発信、相談支援体制の確立である。
連携の対象は、がん拠点病院(国指定、小児、地域がん診療病院)である。まずは、18施設から開始して、必要があればその後広げていく。担当する場所は各拠点病院のがん相談支援センターとした。情報共有のデータとなるのは、国立がんセンターが中心になって運用しているがん情報サービスである。今年の2月から「希少がんの病院を探す」というサイトがでたので、希少がん毎の症例数、対応可能な診療、放射線、手術といったことが一覧として閲覧できるので、そのデータをがんセンターでまとめ、一元的に管理をして、各拠点病院のがん相談支援センターで共有し、相談に来られた医療者であるとか、患者さんに提供していく。兵庫県の希少がんの診療体制の情報を公開していって、早く診療に繋げることができるようにしようと提案した。基本的には参加全施設から「参加したい」と前向きなご意見をいただいた。その中で、次にあげる様々な要望も出てきた。①希少がんに対応している病院を探すという部分で、データベースに載っていない希少がんについても情報を共有してほしい。②希少がんの患者さんを紹介する前に、実際どのような対応をしたらいいかという紹介前の相談の窓口になっていただきたい。③専門病院で治療した後、このネットワークを通じ、地域の病院で継続的な治療を行いたい。
このあたりを踏まえて、今後の進め方としては、希少がんの診療可能な施設のリスト化を行って各施設に提供し確認いただく、各施設の意見を集約し、次回以降の開催を計画するということになった。
〇補足
希少がんについては、国がネットワーク作りを始めており、全国で7つ生活拠点病院というのを指定している。近畿の希少がんネットワークも作り始めており、兵庫県でも必要であるということで活動を始めた。これから随時報告もしていくのでよろしくお願いいたします。
・姫路市遺伝性腫瘍症候群の検査等助成事業について(資料6-3/PDF: 178KB)
姫路市では令和7年4月から新しく「姫路市遺伝性腫瘍症候群の検査等助成事業」を始めている。対象者は遺伝性腫瘍症候群発症者の血縁者(父、母子、兄弟)で、18歳以上の姫路市民の方、かつ遺伝性症候群を発症していない方である。助成内容は、遺伝カウンセリングを2回、遺伝学的検査を1回とし、前者は上限額15,000円、後者は50,000円までとしている。医療保険が適応されないため一部助成となっている。申請書類の中に、臨床遺伝専門医もしくは遺伝性腫瘍専門医の先生にご記入いただく書式もある。そのため、姫路市では、こういった検査カウンセリングができる医療機関の把握をさせていただきたく、この会終了後、アンケートにご協力をお願いしたい。助成の申請書類は、ホームページからダウンロードできる。全ての遺伝性腫瘍症候群の方を対象としているので、該当の患者様やご家族の方がおられたら、ぜひご紹介していただきたい。
〇意見
姫路市は先進的なことにすごく取り組んでいる。子宮がん検診の単独検診も全国でも先駆けて導入を決定されている。この遺伝性腫瘍に関しても通常保険適用がない。姫路市の取り組みから、また、さらに兵庫県全体にそういう助成が広がればなと思うので、啓発をしていただければと思う。
・肝炎友の会からの報告(資料6-4/PDF: 196KB)
今年度4月のがんの診療連携協議会で出した資料ですが、①75歳年齢調整死亡率(部位別)、②近隣県死亡率順位、③都道府県別がん検診受診率(兵庫県)、参考資料として③の東京都、を紹介する。
部位別がん死亡率を見ると、肝臓と肺は死亡率が減ってきている。改善が必要なのは、食道と膀胱である。肝臓については、肝がん対策で非常に力を入れてきた結果であるかなと思う。検診率については、国民生活基礎調査表から引用している。兵庫県では検診受診率が非常に低いことがわかるので、やはり周知が必要である。がん教育を工夫することで不幸な人を減らすことができると考える。
〇意見
- ⇒ やはりがんによる死亡率を下げるには、検診を受けることが一番の近道であると思うので、市町村、あるいは県に対して、検診の啓発の方をお願いしていきたいと思う。
- ⇒ 国際的に言うと、胃がんとか大腸がんをあげると、胃がんは他国にも生存率で劣っているし、大腸がんに関しては先進国で一番生存率が悪い。つまり、死亡率高いというのが日本の実態なので、何とかしていかないとダメだと思っている。兵庫県の検診率がこれほど悪いというのはちょっと愕然とした。課題が山積なんだろうと思うが、1つ1つ課題を見つけてそれを潰していくという作業が必要なのかなと思って大変勉強になった。ご報告ありがとうございました。
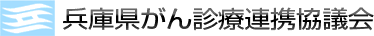
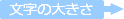




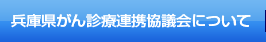
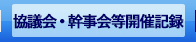


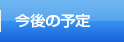
 令和7年度 第1回 兵庫県がん診療連携協議会幹事会 議事録
令和7年度 第1回 兵庫県がん診療連携協議会幹事会 議事録