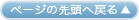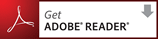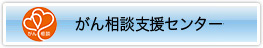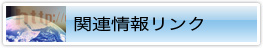第19回兵庫県がん診療連携協議会(以下、協議会)が令和6年4月11日(木)にWeb開催された。兵庫県内の国指定がん診療連携拠点病院、がん診療病院、小児がん拠点病院及び関係団体の代表者等、委員28名のうち、代理出席を含めて25名の委員が出席した。
(1)前回幹事会及び協議会議事録の確認
昨年4月13日開催の協議会、6月8日開催の第1回幹事会、今年2月8日開催の第2回幹事会のそれぞれの議事録は、協議会のHPに掲載されているので確認いただきたい。今回も、議事録はHPに掲載を予定しているので了承願いたい。
(2)がん対策について (資料2/PDF: 422KB)
①兵庫県内のがん診療連携拠点病院等の指定状況について
がん診療連携拠点病院等の指定状況は、国の整備指針に基づいて二次医療圏ごとに原則1箇所ずつ拠点病院を整備することとなっているが、令和6年4月1日現在、国指定病院が18施設ということで、そのうち丹波圏域で変更がありました。兵庫県立丹波医療センターが地域がん診療病院に指定され、兵庫県立がんセンターと連携の下で質の高い医療を提供することになった。その他の県指定拠点病院等については、従来通りである。
②第6次兵庫県がん対策推進計画について
前回の2月の幹事会で説明しているが、パブリックコメント等を踏まえて今回計画策定となったので説明する。
がん対策基本法12条に基づくの都道府県計画は令和6年から令和11年までの6年間になっており、検討体制は健康づくり審議会対がん戦略部会で審議いただき策定した。
がんの年齢調整罹患率・死亡率の状況に関して、人口10万人当たりのがん年齢調整罹患率では、兵庫県は全国より死亡率が高く、令和元年で全国32位となっているが目標は全国10位までを達成するよう取組んでいく。75歳未満年齢調整死亡率では、兵庫県は全国平均を下回っているが、目標は全国平均のマイナス5%以上としており、これを達成するため引き続き取り組むこととしている。
第6次兵庫県がん対策推進計画の概要については、全体目標としてがんによる罹患者・死亡者の減少を実現し、がん患者一人一人に寄り添い、誰一人取残さない兵庫県の実現を果たすことにしている。全体として4つの柱、①がん予防の推進、②早期発見の推進、③医療体制の充実、④がん患者が安心して暮らす社会の実現に取り組むことにしている。そして5番目に⑤がん対策を総合的に計画的に推進する事項として新感染症発生・まん延時や災害等を見据えた対策に取り組むことにしている。
改訂の視点では、がん予防の推進、早期発見に関して、国のがん検診受診率の目標が60%になったことを受けて、これまでの目標50%を60%に新たに設定した。患者・家族に寄り添った取組推進では、アピアランスケアと自殺対策を新たに追加した。その他ロジックモデルの作成については、がん施策進捗管理と評価に有効でPDCAサイクルを円滑に回すため、111の指標を設定した。
がん予防の推進の柱では生活習慣予防の健康づくり、受動喫煙防止等に基づく対策を推進していく。早期発見の推進では、がん検診にさらに取組むため、重点市町の指定や市町の取組を促進していく。一般県民には企業との連携、SNS等を活用したがん検診をさらに促進していく。医療体制の充実については、個別がん対策の推進として小児・AYA世代、高齢者等のライフステージに応じた対策ということで、妊孕性温存治療に取組む。また、拠点病院のチーム医療の整備、専門的な知識を有する医療技術者の育成を進める。がん患者の療養生活の質の向上では、がんと診断されてからの緩和ケアをさらに進めていく。がん患者が安心して暮らせる社会については、アピアランスケア対策、がん患者とその家族への就労支援、全国がん登録の推進などに取り組むことにしている。がん対策を総合的に推進するための事項として、感染症発生時や災害等を見据え、感染症が発生した時にも医療提供体制をしっかり支えて対応することを盛り込んだ。
がん診療連携拠点病院等に関する整備指針の改訂については、厚生労働省の第15回がん診療提供体制のあり方に関する検討会資料を改変したものである。現状では、これまでの拠点病院の整備指針は4年に1回、直近では令和4年8月に見直される一方、がん対策推進計画の計画期間は6年間で、計画期間と指針の見直し期間が合っていないことから、がん対策推進基本計画で定めた医療提供体制に係る取組が整備指針に反映できないので、今後の対応として成人関係については整備指針の見直し期間を6年毎として基本計画の見直し期間と一致させることになっている。なお、小児とゲノム関係は、従来とおり医療提供体制の変化に応じて柔軟に見直すことにしている。
がん対策推進計画と整備指針の改訂スケジュールは、令和5年度から第4期のがん対策計画が進んでおり、令和11年度に見直しされることになっている。整備指針についても令和11年度から6年間として一致させることになっている。
がん検診については、国が定めた「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づいて胃がん検診、子宮がん検診、肺がん検診などを実施いている。このうち、子宮頸がん検診については「がん検診あり方に関する検討会」の議論を踏まえてHPV検査単独法を追加し、令和6年4月から適用する。改正前は細胞診2年に1回であったが、要件を満たした自治体はHPV検査単独法を5年に1回ということで実施する。なお、この検査法は検診結果によって次回の検査時期、検査内容が異なるため、適切な受診勧奨が行われなければ十分な効果が得られないことから、市町村の検診実施機関等の制度管理が重要となるので、この点に留意しながら検診を導入していくことになる。
(3)協議会会則の改正について(資料3/PDF: 324KB)
今回の協議会改正は、昨年4月に兵庫県立丹波医療センターが、特例型の地域がん診療連携拠点病院として1年間指定されていたが、本年4月からは地域がん診療病院に指定されたことに伴う改正になる。会則は、別表の地域がん診療連携拠点病院における丹波圏域の兵庫県立丹波医療センターを削除し、地域がん診療病院に丹波圏域として兵庫県立丹波医療センターを挿入する。なお、会則の改正施行日は、令和6年4月11日とします。
※議長から兵庫県がん診療連携協議会の組織体制、幹事・委員会の名簿等について説明があった。
(4)協議会・幹事会並びに各部会の令和5年度活動報告及び令和6年度活動計画
(資料4/PDF: 1,250KB)
①「協議会・幹事会」関連
令和5年度の活動報告は、4月13日に協議会、6月8日に第1回幹事会、2月8日に第2回幹事会をWebで開催した。当協議会主催の第13回「ひょうご県民がんフォーラム」は、10月21日に加古川中央市民病院の担当で開催した。
令和6年度の活動計画は、協議会は本日4月11日に開催、第1回幹事会は6月6日にWebで開催予定、第2回幹事会は開催日が未定だが、来年2月頃に開催の予定。本年度の「ひょうご県民がんフォーラム」は、兵庫医科大学の担当で10月19日に「がんと診断されたら~患者力を高めるには〜」をテーマに開催を予定している。
②「研修・教育」部会関連
令和5年度は、「がん看護コアナース育成セミナー」は8月25日、9月1日、9月8日に、「患者から死にたいと言われた時」「がん患者の生活暮らしを支える」「事例検討会」(グループワーク)をZoomで行った。「研修・教育部会セミナー」は10月7日に「がん診療におけるAIの最新活用」をテーマにハイブリットで開催。会場14名Web 61名の参加があった。「放射線セミナー」は10月14日に「肝臓がんの診断と治療-update-」をテーマにハイブリットで開催。会場55名、Web 147名の参加があった。「検査セミナー」は12月2日に「初診時からのゲノム医療~婦人科ではどのように治療計画をたてるのか〜」をテーマにハイブリットで開催。会場34名、Web 56名の参加があった。「薬剤師セミナー」は2月17日に「婦人科がん治療」「irAE対策」をテーマにハイブリットで開催。会場50名、Web 55名の参加があった。第9回兵庫県がん化学療法チーム医療研修は11月12日に「がん治療における妊孕性温存」をテーマに開催を予定していたが、諸般の事情で開催できなかった。ひょうご県民がんフォーラムは11月21日に「手術、薬だけじゃない がん治療」をテーマに加古川中央市民病院の担当で開催。会場85名、Web 45名の参加があった。今年度の反省ですが、がん看護コアナース育成セミナーの今後の改善内容で、オンラインでの開催に加え希望者の見学実習を受け入れる企画をするということ。兵庫県がん化学療法チーム医療研修会が開催できなかったのは残念であった。他にハイブリッドで多くの参加者があるので、今年度もハイブリッド形式を維持して頂きたい。
令和6年度の計画は、「がん看護コアナース育成セミナー」は11月22・29日、12月6日に講義と事例検討会を予定。3日間に加え希望者への体験研修を11月11~15日の予定で実施。「兵庫県がん化学療法チーム医療研修会」は、昨年度開催できなかったテーマ「がん治療における妊孕性温存」で11月に開催を予定。「研修・教育部会セミナー」は10月5日神戸市教育会館大ホールで、「消化器がんに対するロボット手術の現状と未来」をテーマに川崎病院に企画をお願いし、ハイブリット方式で予定している。「放射線セミナー」も10月12日に神戸市教育会館で開催予定。テーマ、開催方式等は未定。「検査セミナー」は12月7日に予定。会場、テーマ、開催方式は未定。「薬剤セミナー」は1月18日又は2月8日のいずれかに開催。会場、テーマ、開催方式は未定。「ひょうご県民がんフォーラム」は10月15日に「がんと診断されたら~患者力を高めるには〜」をテーマに兵庫県看護協会会館のハーモニーホールで、兵庫医科大学が担当して開催。開催方式は未定。
③「情報・連携」部会関連
令和5年度活動報告は、概ね予定どおり部会を年4回開催した。内容は就労支援やピアサポーター、認定相談員研修など情報連携部会として実施しなければいけない項目である。事務局会議も予定とおり毎月開催した。これらについては、昨年度の課題となっていた情報・連携部会員の負担軽減策ということで、昨年12月に臨時部会総会を開催し、現状把握と対策について検討し、2月の幹事会でも承認いただいた内容を後ほど報告します。
ピアサポーターについては養成まではするが、その後のフォローアップを病院だけで実施するのは難しく、昨年度はひょうごがん患者連絡会で独自にピアサポート支援をして頂き、患者さんの支援とピアサポーターのトレーニングを合わせて行ってもらっている。これは今後も実施されると聞いているので、情報・連携部会としても連携していきたい。資料はピアサポーターをどう育成するか、今後病院としてどう活用していくか仕組みがまだ整っていないので、この体制について課題を検討していきたい。また、就労支援については、昨年度と同様にハローワークとのオンライン面談など継続して実施したい。
情報・連携部会員の業務負担軽減については、昨年度に指摘を受け、がん相談支援センターの相談員(実務者)全メンバーに現状調査のアンケートを行い、実務者の負担が課題との意見が寄せられた。協議の結果、対策として部会業務のスリム化と相談支援センターの責任者の出席を依頼する内容の改革案が承認となった。
アンケートは、ほぼ100%に近い人が部会活動に負担を感じると回答し、問題は業務量の調整確保に配慮があると6~7割が回答しているが、8割近くの人がサービス残業や自宅での作業が生じていると回答している。残念ながら配慮があっても労務管理の改善に至っていないので、働き改革が重視されている状況では根本的な変更が不可欠という結論になった。
部会の構造は、例えば緩和ケア部会では緩和ケアの責任者(組織の長など)が参加することが多く、対外的或いは組織的に動いて企画を通すことに慣れているが、情報・連携部会の責任者(副院長など)では、実情とかけ離れた議論になってしまい、相談が患者に繋がらないことで相談員である実務者が参加することになり、結果、現状の課題に沿った活動はできるが、一般社会に通用する成果物、特に病院を超えて市県単位で通用する内容のものも作成し、手続きしなければならなくなった。課題として管理的立場にない相談員のグループが病院を代表した公的な企画案をまとめるのに何回も修正とかOJTのようなことをしなければならなくなって事務局会議に出す前に差し戻しが頻発するため、方向修正が困難になって事務局会議を毎月開催することとなった。一方で情報・連携部会は、各相談員の通常業務量・スキルを把握しながら勤務を調整する立場にないため、業務量とタスクのミスマッチが発生した。
情報・連携部会の業務軽減案として、部会を年4回から2回に午前と午後を使って減らす。そして事務局会議を毎月から隔月の半分に減らすことになっている。そのために実務者に加えて、がん相談支援センターの方針決定や相談員の労務管理を行い、実質的業務に携わっている管理的立場の人に参加をお願いしたい。
情報・連携部会の令和6年度の体制は、就労支援は3か年計画の最終年度になるので、グループ数は変わらない。部会の日程は9月と3月、事務局会議は奇数月、就労関連とピアサポート関連はこれまでどおり進める。場合によっては対面で部会を行うことを想定している。5月の事務局会議では管理的立場の方にも参加いただき、対面での開催が適切かどうかも議論したい。PDCAサイクルも添付のとおり策定している。
④「がん登録」部会関連
令和5年度は、がん登録部会を6月27日に開催し、院内がん登録全国収集における都道府県推薦の取扱い等(5月16日に開催された国の連絡協議会がん登録部会での内容)の情報提供を行った。院内がん登録実務者ミーティングは11月14日と2月2日にそれぞれWebで開催した。2月に検討した2021年症例施設別部位別がん登録件数のホームページ公表案については、兵庫県がん診療連携協議会ホームページに既に公表している。同じく実務者ミーティング事務局会議も2月2日に開催した。都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会がん登録部会は5月16日にWeb開催され参加した。データ利用の提供審議会の進捗と今後についてなど報告があった。その他、各医療機関におけるがん登録の状況把握アンケート調査を実施した。全国がん登録実務者研修会は9月21日から10月3日にかけて動画配信で実施した。
なお、がん登録部会のアンケートは49の施設に対し、8月から9月にかけて実施した。回答は35施設、74.4%の回収率だった。人員配置の状況では5人以上従事する医療機関は8か所、専任の従事者がいない医療機関は6割を超えて最も多かった一方、専従では従事者が1人の医療機関は4割を超えて最も多かった。個人情報の取扱い情報では、情報漏洩時の対応手順とか独立したパソコン環境など7割は対策が進んでいる一方、個人情報の利用場所や保存区画が他の業務から独立した部屋となって入退室が整備されていない医療機関は7割であった。がん登録推進法20条に基づく都道府県がん情報の申請予定があるのは25%程度で申請があまり進んでいないという結果であった。がん登録に対する院内の理解では8割が理解を得られているという回答だった。
令和6年度は、がん登録部会は6月に開催する。院内がん登録実務者ミーティングは11月及び2月に開催する。全国がん登録に関する研修会は開催日程、内容等は未定。
がん登録部会のPDCAサイクルは、「がん診療情報を収集・分析する体制整備」「がん登録実務の精度向上」「全国がん登録情報の予後情報還元申請」の3つを課題にあげ、収集分析はホームページにデータを掲載、実務の精度向上は実務者ミーティングの開催。情報還元申請に関してはアンケート調査の実施により取り組みを進め、概ね達成したと考えている。令和6年度もこの3つについて引き続き取り組みを進める。
⑤「緩和ケア」部会関連
令和5年度活動報告は、国の連絡協議会第11回緩和ケア部会にWebで出席した。当協議会の緩和ケア部会は年4回Web開催した。以下は小集団活動の個別の活動になるので、詳細な報告は別途資料を添付している。症状緩和のための専門的治療体制に関する実態調査ということで、がん疼痛に対する神経ブロックやIVR放射線治療に関し各施設の実態を調査し、がん診療連携協議会のホームページ等に公開している。緩和ケアフォローアップ研修会は12月2日に開催。また、兵庫県緩和ケアチーム研修会は、加古川中央市民病院の担当で2月4日にWeb開催した。緩和ケア研修会指導者の会は、1月31日にWeb開催した。緩和ケアチームピアレビューの実施は、兵庫医科大学病院と県立がんセンターの2施設を対象に実施した。各小集団活動のグループ活動の統括ということで、部会運営事務局会議を毎月Webで開催している。緩和ケア研修会は、各施設で年一度開催頂いている。開催実施と今年度の予定については、添付資料のとおりです。
令和6年度の活動計画は、令和5年度実施結果を踏襲して小集団5で計画している。
PDCAサイクルは、昨年度は「緩和ケアチームピアレビュー」と「がんの痛みに対するインターベーション治療」の2つを課題にあげて概ね達成したが、今年度も活動を継続する。なお、各グループの研修会等の活動の詳細の説明は省略する。資料は緩和ケアチーム研修会(SG1)、フォローアップ研修会(SG2)、緩和ケア研修会(SG3)、緩和ケアチームピアレビュー(SG4)で、緩和ケア研修会はがん診療連携協議会のホームページにアップされている。緩和ケアチームピアレビューは昨年度2施設で実施。今年度も国指定の施設で実施したい。当部会でも業務改善を考え、出来る限り平日の業務時間内での活動に協力をお願いしたい。ピアレビューは、国の指針においても第三者評価が求められているので、ご理解、ご高配をいただきたい。がんの痛みに対するインターペンショナル治療(SG5)に関してもホームページに公開している。各施設の治療内容は○、✕で実態が表され、詳細は各施設のホームページにリンクできるよう調整して情報公開できればと考えている。今年度のPDCAサイクルは、今5つの小集団が動いており、各集団毎にテーマを決めている。
兵庫県への要望として、がん対策ロジックモデルには緩和ケア領域に関して指標が出ていると思うので、その指標を参考に改善を考えている。PDCAサイクルを回していくためにも、その情報をいただきたい。
⑥「地域連携」部会関連
令和5年度の活動は、各施設のがんパス使用状況を確認検討した。令和4年度の登録件数は1,467件で、内訳は記載のとおりであった。また、各がんの地域連携パスの見直しと修正を進めた。がん地域連携についてアンケート調査を行ったが、48施設中9施設がWebで退院前カンファレンスを実施していた。令和4年度の遠隔診療実施件数は570件であった。
令和6年度活動計画は、前年度と同様にアンケートによる地域連携パスの使用状況を確認し、パスの問題点を検討、抽出する。
PDCAサイクルは、課題を3つ定めた。1つ目は、パス利用の各施設間格差を改善する。アンケート調査によると、パス利用を積極的に活用している施設では、活用がすごく進んでいる。施設によって格差があって、活用が進んでいないところの課題抽出とその提案を検討する。2つ目は、パスの課題の抽出、改訂、活用ということについては、各部門の各領域で内容を精査し、ワーキンググループで検討する。既に前立腺がんと肺がんは改訂が行われ、前回の幹事会で報告があった。胃がんに関しては術後パスの改訂案がほぼ出来上がり、次の幹事会で報告が検討されている。また、パスの研究については、部会長から県立病院学会、或いは日本クリニカルパス学会で一部発表を行ったと聞いている。3つ目は、がん地域連携の課題の共有と改善では、リモート連携に関してアンケート調査を行ったが、新型コロナが落ち着いてきたこともあって、あまり進展していない。がんのゲノム医療については、これからの分野で様々な課題があるが、スムーズな連携に向けて提案をしていきたい。
(5)がん生殖医療について (資料5/PDF: 347KB)
兵庫県がん・生殖医療ネットワークの運営状況
資料は2023年1月から1年間でカウンセリング実施数が女性53名、男性48名で、実際希望されたのは女性49名、男性は全員で、原疾患は乳がんが26名で最多、男性では白血病、リンパ腫、血液疾患が多い状況です。受精卵凍結では、英ウイメンズクリニック7件、兵庫医科大学で0件、卵子凍結が最近増えている印象です。卵巣凍結も兵庫医大が10件、両方行った人がいるので、卵巣凍結は11件、精子凍結も増えてきている印象がある。英ウイメンズクリニック、兵庫医大、兵庫県全体の妊孕性温存症例は棒グラフのとおりです。卵子凍結(29)が今増えて、精子凍結(44)もこのよう状況になっている。過去2016年から2023年の妊孕性温存実施件数は右肩上がりではないが、だいたい40例前後で推移している。2021年から妊孕性温存の研究促進事業が開始されて、患者は公的助成金が得られるようになった。2016年1月に兵庫県がん・生殖医療ネットワーク設立されて7年間の23年10月までに、受精卵凍結は75例、移植したのは30例、そのうち妊娠成立は22例にということになった。卵子凍結では移植患者数は7人(6.2%)、妊娠率40%くらい。卵巣凍結で移植した人はまだいない。卵巣凍結は配偶者がいないことと、卵巣凍結は若年でも適用され、長期フォローの後に適用される可能性があるので、引き続きこれに対応していく必要がある。
なお、今まで英ウイメンズクリニックと兵庫医大が公的助成資金を受けられる対象施設だったが、徐クリニックも諸手続きが済み、兵庫県がん・生殖医療ネットワークに参加となって、今は3施設で運営している状況である。
(6)がん患者医科歯科連携協定について (資料6/PDF: 150KB)
令和5年度は、前年と同様にがん医科歯科連携の知識を深めるため、DVD講習会を年に1回実施した。がん患者の医療施設への協力歯科医の医療機関の情報提供も行った。県委託事業で、口腔がん対策推進事業として講義を7月9日に1回、実習を2回実施して、口腔細胞診と口腔蛍光観察を行った。
令和6年度も、口腔がん対策として、6月29日に東京歯科大学名誉教授の藤原先生に講義を依頼し、実習は今年度1回、口腔細胞診と口腔蛍光観察を実施する。また、各がん患者の医療施設に協力歯科医の医療機関の情報提供を行う。
(7)小児がんの進捗状況について (資料7/PDF: 3,000KB)
第四期がん対策基本計画において、小児がん治療がどのように位置づけされているか確認すると、第3期小児がん拠点病院事業の期限は2027年3月までとなっている。第四期がん対策推進基本計画は、均てん化、集約化。それは小児がん・AYA世代のがん対策ライフステージに応じた療養環境の支援等々が挙げられている。まず、均てん化と集約化は全国の小児がん拠点病院の集約化という状況で、兵庫県立こども病院は西日本で多くの患者が集まっている病院である。それらを支える診療体制は、小児がんの血液がん専門医が5名(4月から6名)、この体制で診療にあたっている。
令和5年度は、これまで行ってきた活動を加速したいと考えている。特に陽子線治療に力を入れていく。また、高校生を含む療養関係の充実を行ってきたが、コロナ禍においてもこども病院では面会、付添いは可能な体制となっている。若年者について小児に寄り添った診療ができる環境を整備している。昨年は小児、コロナの入院を重点的に受け入れ、流行全体の波に飲み込まれ、スタッフの就業制限も多かったが、入院制限や病棟閉鎖を最小限にとどめて概ね診療機能を維持して進めることができた。小児・AYA世代のがん患者にとって面会と付添いの環境を維持して診療できるのはメリットがあると考えている。
最近、カテゴリー1-Aという連携病院を新設した。もともと小児がん拠点病院事業では、拠点病院に多くの患者を集約化したいと考えられていたが、物理的に難しいということで、拠点病院と同様の機能を有する準拠点病院としてカテゴリー1-Aを設定して多くの患者をカバーする計画に軌道修正された。概算で小児がんのおよそ7割を拠点病院とカテゴリー1-Aでカバーできる計画になっている。カテゴリー1-A施設として、神戸大学医学部附属病院、県立尼崎総合医療センターに、今年度は新たに県立はりま姫路総合医療センターが加わり、県内13施設が県立こども病院と連携して小児がんの治療にあたり、外来支援とかWeb会議などを通して医療連携を図っている。
一方、他の都道府県を見ると、県内に拠点病院もカテゴリー1-Aも存在しない都道府県が多く、どのように最適な小児医療を提供するかという新たな問題が指摘されている。それに対応するため、県立こども病院は近畿の4つの拠点病院で地理的に一番西に位置することから、多くの中国・四国地域の病院と連携し、集中治療を含むあらゆる小児がんに対応できる環境を整備している。例えば小児の陽子線治療についてはかなり広範囲から患者を集め、神戸陽子線センターとの協力で、全国の小児がん陽子線治療として一番患者さんが集まる施設となっている。それ以外に人材育成として、指導医が不足している地域、特に今年度から香川県立医科大学小児科と連携して、専門医の育成に努めている。
2022年12月に遺伝子改変T細胞療法(CAR-T細胞療法)の施設承認を受けて治療に参入し、昨年度は3例実施した。中には規格外のものもあるため第3相Bの治験を行っていて、このような治験を含めてCAR-T細胞療法について力を入れていきたい。また、ゲノム医療について、小児がんについては少し事情が特化するところがある。TOP2という小児がんの診療に有用な遺伝子パネルが開発されており、この臨床実装には十分に実行可能性があることが確認できたので、いくつか課題があるがジェンマイントップという商品名になっているが、小児がんに特化したガイレージパネル検査が活用できるようになった。小児がんでは9割を超える症例で病理の中央診断が行われているところで、そのような病理の診断と組合わせて出口戦略を考えて行こうとしているところがある。昨年度、ファデーションワンのリキッドが小児に対して適用拡大になり、ガーダントのパネルも使えるようになった。ジェンマイントップが小児がんに特異的なものとして昨年8月に、これらを踏まえていくつか新規に保険適用が得られるような分子標的治療剤が出ているので、成人領域の先生方と協力しながら患者に提供できるようにしていけばと考えている。
国立成育医療研究センターと国立がん研究センターを中心に、小児がんについては病理の中央診断というシステムが活用されていて、初診症例の9割以上の症例が中央診断を活用している。この病理診断とゲノム診断を結び付け、臨床情報収集、検体保存を含んだグランドデザインを作ることが国をあげて行われている。
希少疾患である小児がんの治験について、それを運用すべき人材育成を行っていくことで、国立がん研究センター中央病院で短期或いは長期の研修生を受け入れてもらう状況になっていて、こういったことに対応できる人材を育てていきたい。県内では県立こども病院が中心になって小児がん、小児血液がんに対する治験を展開しているので、対象の患者がおられたら相談頂きたい。
療養関係について、当院では入院される患者はどうしても親御さんから話を聞いたり或いは同意を得なくてはいけないことがありますが、兄弟がいるため両親揃って話が聞けないことが多く、2021年3月から兄弟支援制度を開始し、兄弟を保育所に預かるサービスを始めている。また、高校生を含めてICTを活用した遠隔事業も展開し、行政、原籍校、医療機関が一体となって遠隔授業を進めている。県立病院群では、Wi-Fiを引く作業が順次行われていて、当院では3月末から病院病棟全体がカバーされ、これが遠隔授業に活用されている。
小児がんを経験した患者の移行期医療は、成人期になってもサバイバーとして様々な問題を抱えることは知られていて、神戸大学医学部附属病院の腫瘍血液内科或いは小児科の先生方の協力を頂き、神戸大学病院移行期医療支援センターの力を借りてシームレスなトランジションが行われるようになった。
(8)その他
兵庫県のがんゲノム医療の推進について
昨年度に紙ベースで依頼、幹事会でもお話したが、ゲノム医療遺伝子治療、これは国の基本計画の中にも挙げられ、今後益々発展し、ニーズも増えると考えられる。これに関連して、治験も国立がん研究センターが、どこでどんな治験が行われているか一覧表にし、将来的にはわざわざ調べて県内から東京まで行って治験を受けることもなくなり、リモート治験ということになると考える。同じようにゲノム医療も県内で完結できるようにしたいと思う。それには、がんゲノム医療の連携病院、或いは拠点病院、中核拠点病院になる必要がある。現在、県内にがんゲノム医療の拠点病院が2つ、連携病院が7つある。国指定のがん診療連携拠点病院は、これまで必要だった治験の縛りがなくなり、ゲノム医療連携病院になりやすくなったので、これを目指していただきたい。もちろんそのためにゲノムコーディネーターや遺伝カウンセラーといった職種が必要で、そのための予算とマンパワーが必要になるのですぐには難しいが、将来を見据えてできる限りそれを目指して検討をお願いしたい。
抗がん剤手帳の作成について
昨年度の幹事会でもアナウンスさせていただいたが、異時性の重複がんで、過去に抗がん剤治療をされて数年後に別の癌で抗がん剤治療をされる方が増えている(特に血液がん、乳がんなど)。当院の腫瘍循環器内科から、一部の抗がん剤(アントラサイックリン系など)では、蓄積性の毒性があるが、データがないケースがあり困っているとの意見があった。将来的にマイナンバーカードで全データが紐づけできれば良いが、すぐには期待できない。抗がん剤に関して手帳のようなものが作れないかということがあって、この協議会で了解が得られれば当院の腫瘍循環器科で叩き台のようなものを作らせていただき、第1回又は第2回の幹事会で案を出させていただき、これをどのように活用するか相談したい。
兵庫県の75歳未満がん年齢調整死亡率について
兵庫県の75歳未満がん年齢調整死亡率が良くなって全国で16位になった。今までおよそ25位くらいだったが、胃がん、肺がん、悪性リンパ腫が改善されたことでこの順位になった。前立腺がん、膀胱がんは36位くらいで、これらが改善されればさらに順位が良くなると思われる。先ほどロジックモデルの話が出たが、やはり75歳未満がん年齢調整死亡率の順位が良くなることだと思う。また、緩和ケア、就労支援について人々が満足いくかどうかということがロジックモデルの最終評価と思う。がん検診は目標値を50%→60%にする話があったが、兵庫県の場合はどのがん種も40%前後で、全体的な底上げを行えば75歳未満がん年齢調整死亡率は10位くらいになる。近くの府県では滋賀、京都、三重、奈良、岡山などは一桁順位で和歌山、大阪は順位が悪いが、兵庫県も検診受診率の改善、前立腺・膀胱がんを改善すれば、順位は良くなる。
※疾病対策課のコメント
令和4年度で少し改善しているが、先ほど資料で紹介したとおり全国平均と差がある。がん検診受診率が40%とかなり全国的にも低い水準です。第6次兵庫県がん対策推進計画を踏まえて、関係団体等に検診の必要性をPRするとともに、県民へのSNS活用など がん検診受診率を向上させ、さらに年齢調整死亡率もマイナス5%以上達成できるよう取組んでいきたいので、今後とも各委員の皆さまのご指導、ご協力をお願いしたい。
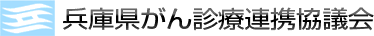
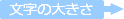




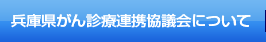
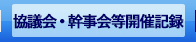


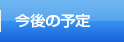
 第19回 兵庫県がん診療連携協議会 議事録
第19回 兵庫県がん診療連携協議会 議事録